スポーツ記者となり三年半、多くのアスリートを取材する中で必ず恩師の話が出てくる。今春、天理教校学園ラグビー部OB・梶間歩さんに取材した際、幾度となく挙がったのが紙谷直樹先生(現・日本航空石川高校ラグビー部監督)だ。梶間さん越しに映る紙谷先生はハードワーク、徹底したタックルを指導する熱血というイメージの一方で、絶対的な信頼や厳しさの中に温もりさえも感じさせてもらった。
小柄な素人軍団が強豪校相手に躊躇なく「くるぶしタックル」を突き刺す姿に惚れ込んで以来、教校ラグビー部の大ファンである筆者が、名将のストーリーに迫る。

同好会から始まった親里高校ラグビー部
―ラグビーを始めたのはいつからですか?
高校から始めました。兄は大阪工大高校(現・常翔学園、以下・工大高) ラグビー部が初優勝したときのメンバーだったので、その姿に憧れて工大高ラグビー部に入部しました。本当に厳しい練習でしたが、選手として鍛えてもらいました。
―天理高校ラグビー部は選択肢になかったんですか?
天理高校I部(以下・天理高校)も強かったですが、兄の影響で工大高に憧れていましたね。卒業後は天理大学ラグビー部にお世話になりました。部員は30人程度でしたが、同志社大学、京都産業大学、大阪体育大学としのぎを削った時代でした。ライバルチームのおかげで大学でも鍛えてもらい、関西代表候補メンバーに選んでいただくことができました。
―大学卒業後は実業団でプレーされたんですか。
近鉄ライナーズでプレーしたかったんですが、進路が決まる前に、学校本部から「天理教校附属高校(以下・附属高校)のラグビー部を強くしてほしい」と打診があったんです。かなり迷いましたが、附属高校でお世話になることを決めました。そしたら、新設されたばかりの親里高校に配属されたんです(笑)。
親里高校にはラグビー部がなかったので、1年目は放課後に附属高校でラグビーを教えていました。3年目の冬にラグビー部創部が決まり、4年目から監督をすることになりました。

―創部後すぐに選手は集まったんですか。
親里高校はラグビーの授業があり、あらき寮(男子寮) では階対抗のラグビー大会があったりと、生徒がラグビーに慣れ親しみやすい環境でした。なのでラグビー好きな生徒が多く、「なぜラグビー部がないんですか?」 と聞いてくるので、有志で「ラグビー同好会」を作って私が指導していました。
創部時、部員は同好会出身の7人しかいませんでした。彼らは「自分たちは寄せ集めのガラクタ軍団だ」という気持ちで「ガラクターズ」という愛称で練習に励んでくれました。
タックルで挑み続けた「打倒天理」
―当時はどのような指導をしていたんですか?
とにかく練習しました。当時は天理高校の一強時代で、御所工業(現・御所実業、以下・御所)が強くなりはじめた頃だったので、「親里と御所で天理を倒すんだ」という強い気持ちを持っていました。よく御所のグラウンドに練習に行かせてもらいました。
―紙谷先生といえばタックルの印象が強いです。
ラグビーはとにかくタックルです。「タックルは根性」だと思われがちですが、「タックルは技術」です。タックルするときはボールを持たないので、技術さえ習得したら素人でも絶対にできる。素人軍団が天理高校に勝つにはタックルしかないんです。

―でも、勇気や気持ちも大事だと思いますが。
最終的にはそれも必要です。プロ野球選手はメンタルが必要だと言いますが、技術を習得した上で最後はメンタル勝負になる。タックルも一緒です。最初から勇気だと言うとみんな辞めちゃいます(笑)。
例えば天理高校と対戦する際に、「敵との間に広いスペースがあるとタックルに入っても負けるけど、スペースを詰めたら良いタックルに入れる」と考えます。スペースをいかに詰めるかは技術です。それができて最後に勇気を持ってタックルに入るんです。
―私は天理教校学園(以下・教校)の「くるぶしタックル」を見て教校ラグビーファンになりました。なぜ彼らはあのタックルができるんですか?
タックルは分解して教える必要があります。ポジショニングの仕方、プレッシャーのかけ方、スタートの切り方、タックルの入り方、順序立てて教えれば誰でもできます。
そして、タックルに入ったらすぐに立ち上がるのが大切です。15人vs15人なので、相手を倒してこちらがすぐに立ち上がれば15人vs14人になる。常に人数で勝ることが大切です。
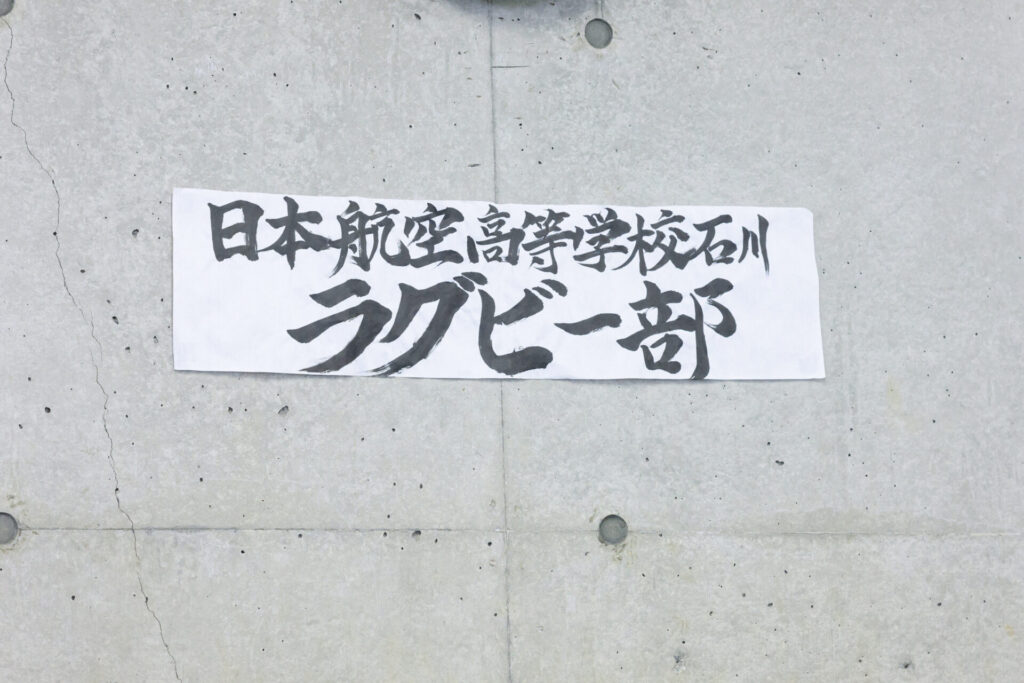

2023 年から日本航空石川高校でコーチ、翌年から監督をつとめる。能登半島地震での被災を経て、ラグビー部は東京都内の施設で生活をしている
―親里高校ラグビー部は、1996年11月、創部3年目で迎えた全国ラグビー高等学校選手権(花園)の奈良県大会準決勝で天理高校と 0-7 という1トライ差で惜敗のゲームを演じています。
とにかくタックルでした。当時の観客の方がいまだに「あの試合が奈良県で1番のゲームだ」と言われます。私もすごいと思いながら見ていました。
我々はタックルしか練習していないし、タックルしか信じるものはなかった。試合が始まり、いざタックルに入ると「本当に俺たちのタックルで倒れるんだ!」と実感していました。選手が試合中にどんどん強くなっていきました。天理の方が圧倒的に強いんですが、後半15分までスコアは0-0、ラグビーの面白いところですよね。
普段冷静で、試合中に声を荒げない天理の田中克己先生が「絶対にボールを蹴るな!」と叫んでいた、それくらい親里が押していましたね。
―そのような熱戦を演じられたのはなぜですか?
信じ込ませることが大切だと思います。普段から伝えていることが、天理戦で実際にそうなり、「ホンマや!」 「いけるぞ!」ってなりました。練習通りにプレーしたら結果が付いてくると勢いつきますよね。
ただ、それでも勝つことはできなかった、天理との実力の差です。選手は泣いていましたが一方で満足そうでした。
指導者としての失敗、そして学校統合
―紙谷先生にとっても転機になった試合だったんですね。
実は、手応えを感じたからこそ失敗してしまいました。当時、私は27歳と若く「同じ練習させたら次こそは勝てるぞ」と前年同様に厳しい練習をしたら、最上級生が7人中6人退部してしまいました。自分本位の指導で、選手たちが置き去りになっていました。せっかくラグビーを志してくれたのに、彼らを辞めさせてしまったのは若気の至りでした。
―どのように指導方法を変えたんですか?
練習内容は基本的には変わっていません。その中で、選手と話す時間を増やしたり、寄り添う声をかけたり。厳しさの中で、「厳しくない時間」も意識するようになりました。

-2005年、親里高校と附属高校が統合しました。同時にラグビー部も統合になりましたよね。
ライバルチームが統合するのは難しいことで、統合当初は選手同士が歪みあっていましたね。よく喧嘩になるので、そのたびに「ラグビーで決着つけろ!」と練習試合をさせていました。
統合したことで部員数が60人以上になり、統合前ならレギュラーだった選手が出れなくなるんです。「絶対に俺が試合に出るんだ!」 というライバル意識がすごかったので、みんな必死に練習していましたね。見る見る成長していき、本当に強いチームになっていきました。
2005年11月の花園予選、準決勝天理戦もすごい試合でしたよ。序盤にペナルティをもらい、確実に3点取るためにペナルティーキックを指示したんですが、選手は「トライ狙いましょう!」と言うんです。そうしたら本当にトライ取って5-0と先制したんです。この試合は1996年のときより勝てるチャンスがあった試合でした。でも勝てなかった (5-17)。選手層も技術的にも当時よりも勝っていましたが、今思うと当時より劣っていたのは練習での追い込み方だったかもしれません。厳しくなかったわけではないですが、その差が最後にでたのかなと。
―その後も教校ラグビー部のレベルも上げる一方で、天理のレベルも上がり差が縮まらない印象がありました。歯痒さはありましたか?
まったくありません。毎年、春の天理戦では大敗するけど、花園予選ではスコアが縮まり強くなっている、我々にはそういうストーリーがありました。なので、春に大敗しようが気にしない、絶対に大丈夫だと選手に思い込ませていました。
「天理と御所を倒す」この気持ちは毎年持ち続けていました。それがないとあんなしんどい練習させられないし、選手もついてこられません。

これからも生き続ける教校ラグビー
―紙谷先生にとって教校のラグビーはどんなラグビーでしたか。
「おもろいラグビー」です。ラインアウトで驚くようなサイン出したり、高校ジャパンの大きな選手に、細い選手がタックル一撃で倒したり。観客が「えー!!」と驚いたり、点差は開いても良い試合だったと喜んでくれるのが、私の理想でしたね。
―梶間さんが、「紙谷先生は信仰的にもアツイ方です」と話していました。
そんなことないですよ(笑)。ただ、「お道の教えは絶対に間違いない」という自信はありました。なので、人と話をしていて「良い人だな、魅力的な人だな」と感じてもらって、「あの人は天理教の人だったんだ」と後付けで認めてもらえることが大事だし、人が寄ってきてくれると思います。卒業生には「社会に出たら教校出身と言っても何も通用しない。だけど、行動で『お道の人は素晴らしいな」と認めてもらうことが大事だよ」と伝えていました。

―今後、航空石川でどのような指導をされますか。
航空石川は留学生もいるし、アタックが大好きです。でも、天理高校と試合をすると、天理の早い展開ラグビー相手にボールを奪えないんです。ラグビーはディフェンスが大事なんです、だからタックルなんです。
ラグビーでも教校と同じこと言うてますが、私生活でも一緒です。「人のために行動しなさい」「困っている人がいたらたすけなさい」 「親御さんにも喜んでもらいなさい」と、結局同じことを言い続けています。
―教校ラグビー部が日本航空石川高校で刻まれているんですね!
そう思ってもらえるように頑張ります。

伊勢谷のふりかえり
2012年、花園を目指す奈良県大会1回戦、天理VS教校学園の試合を観戦した。母校・天理高校を応援していたが、どんなに点差が開こうと小柄な選手がタックルに入り続ける。低く突き刺さるタックルで大きな天理の選手を倒していく。いつしか教校を応援して、終了間際にトライを奪った瞬間は涙が溢れた。勝敗を越えた戦う姿勢に心が奪われ、教校ラグビーのファンになった。「結果以上に、過程が人の心を動かす」と教えてくれた。
教校学園ラグビー部はなくなったが、梶間さんの取材を通して「教校学園ラグビー部の精神が社会で生き続けている」ことを知れた。今後もOBたちが社会で発揮し続けてくれるはずだ。
そして紙谷先生とお会いして、教校学園ラグビー部の精神が新たなチームで根付きつつあることを実感できた。それがとてもうれしかった。
花園の舞台で紙谷先生率いるチームが天理高校と対戦するときが楽しみでならない。
(文=伊勢谷和海、写真=廣田真人)

紙谷直樹さん/KAMITANI NAOKI
1967年、大阪府生まれ。高校からラグビーをはじめ、大阪工大高校時代は高校日本代表候補、西日本代表に選出。天理大学でもラグビー部に所属。卒業後、親里高校に赴任、ラグビー部創部に伴い監督に就任。以降、天理教校学園閉校まで監督として多くのOBを輩出。また高校日本代表コーチでユースTIDマネージャーをつとめるなど指導者として幅広く活躍する。2023年から日本航空石川高校ラグビー部コーチに就任、翌年から監督として20年連続の花園出場に導いた。
伊勢谷和海/ ISETANI KAZUMI
1984年愛知県生まれ。天理高校、天理大学卒業後、天理高校職員(北寮幹事)として勤務。好きなスポーツは野球・陸上・相撲・ラグビーなど多岐にわたる。スポーツが好き過ぎて、甲子園で校歌を数回聞くと覚えてしまい、30校以上の校歌が歌える。スポーツ選手の生年月日・出身校も一度見たら覚える。高校野球YouTubeチャンネル「イセサンTV」を開設。ちまたでは「スポーツWikipedia」と称される。








